ハロウィンといえば「仮装」でしょ!
という人が多いと思いますが、そもそもどんなお祭りなのかご存知ですか?皆さんは、どれだけハロウィンのことについて知っていますか?
ここ数年、とても人気で盛り上がってきていますよね。子どもから大人まで幅広く、毎年楽しみにしている人が多いのではないでしょうか。
その由来や起源、本来の意味についてご紹介します!
今年のハロウィンをもっと楽しみたい! っと思っている方はぜひ読んでみてください。
1.ハロウィンとは?
1-1.ハロウィンの起源と由来

ハロウィンの起源は2,000年以上前、現在のイギリスやアイルランドにあたる場所に暮らしていた古代ケルト民族の宗教儀式のひとつである、「サフィン祭」が起源だと言われています。
サフィン祭は、古代ケルト民族の一年の終わり日である10月31日に秋の収穫を祝い、作物を神様に捧げるものでした。
この日の夜には、あの世とこの世の境い目がなくなり、日本で言うお盆のように、死者の霊が現世の家族に会いに来ると信じられていました。
しかし、同時に霊界から「悪魔」「悪い妖精」「魔女」もこの世にやってくるため、作物を荒らしたり、子どもを連れ去っていったりと、悪さをするとおそれられる日でもありました。
そこで収穫祭の夜、人々は仮面を被って仮装し、魔物たちを追い払ったと言われています。
また、魔女や悪霊は人間の魂を奪うと信じられていました。降りてきた悪霊たちに人間であると気づかれて悪さをされない様に仮装していたという言い伝えもあります。
悪魔などが家の中に入ってこないように魔除けの火を焚き、家の外にワインや食べ物などのお供え物を置いて、満足して霊界に帰ってもらえるようにしました。
この魔除けの火が、現代の「ジャック・オー・ランタン」に姿を変え、玄関先に飾られています。
これが現在のハロウィンの由来となったと考えられます。
1-2.なぜハロウィンというようになったの?
やがてケルト人が自然崇拝からキリスト教と結びつき、キリスト教の諸聖人に祈りを捧げる「万聖節(ばんせいせつ)」または「諸聖人(しょせいじん)の日」の前夜祭として行われるようになりました。
Hallowとは聖人を意味する言葉で、「諸聖人の日=All Saints’ Day」は「All Hallows」とも表記されます。
11月1日の「All Hallows」の前夜である10月31日は、「All Hallow’s Eve」といい、これが短くなり、「Halloween」といわれるようになったという説があります。
他にも、神聖な「Hallow」+夜「Evening」=「Halloween」となったという説もあります。
もともと古代ケルトの宗教的なお祭りからスタートしたもので、キリスト教由来のイベントではないことから、キリスト教では宗教的な意味合いは持たないイベントのひとつとして扱われています。
ハロウィンは、発祥の地とされるアイルランドから多くの国に伝わっていますが、それぞれの国の文化と融合して独自の発展を遂げているのが特徴です。
2.なぜ仮装するの?

前述したように、ハロウィンには悪魔や魔女、悪霊がやって来て災いをもたらすとされていました。そこで、身を守るために仮面をかぶったり、悪霊や魔女の恰好をして仲間にみせかけたり、その格好を見て驚いて逃げるようにしたのが、仮装の始まりです。
3.「Trick or Treat(トリック オア トリート)」とは?

海外では「Trick or Treat」と言いながら近所の家を周ってお菓子をもらう風習がありますよね。
『お菓子をくれないと、いたずらしちゃうぞ』という意味です。
その言葉に大人たちは「Happy Halloween!(ハッピーハロウィン)」と答えてお菓子をあげるのが一般的です。
元々は「Souling(ソウリング)」というヨーロッパの風習に由来するという説があります。
これは11月2日の死者の日にクリスチャンが「Soul cake(ソウルケーキ)」を乞いながら家々を渡り歩き、お礼としてその家で亡くなった方の魂に祈りを捧げて、供養をするという風習です。
ソウルケーキを準備していなかった家庭では祈りを捧げることが出来ないため魂が鎮まらず、悪さをすると信じられていたそうです。
ソウルケーキがお菓子に、悪さをする死者の魂は仮装した子どもになってハロウィンの定番として定着したと言われています。
4.カボチャのランタンとの関係は?

ハロウィンのシンボルといえば、カボチャをおばけのように怖い顔にくり抜いて、中にキャンドルを灯したランタンです。
このランタンを、「ジャック・オー・ランタン」という名称で魔除けの役割を持ち、悪霊を追い払う力があるといわれています。先祖の霊が迷わず帰って来るための迎え火としての意味があるそうです。
ジャック・オー・ランタンと呼ばれる由来は、アイルランドの民話に出てくる登場人物が「ジャック」という名前でした。では民話を見てみましょう。
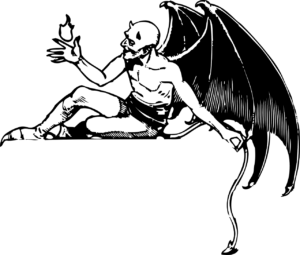
ケチで人を騙し悪事ばかりしていた「スティンジー・ジャック」という男がいました。 あるハロウィンの夜、ジャックは魂を取りにやってきた悪魔と出逢います。 ジャックは悪魔を騙して、10年間はジャックの魂を取らないことを約束させました。 そして、その10年後に再び悪魔が現れますが、またうまく騙して、 「ジャックの魂を永遠に取らない」と約束させたのです。 そんなジャックは死後、ケチで乱暴者だったため天国に行くことが出来ませんでした。 しかたなくジャックは地獄に行き、そこであの悪魔と再会したのです。 ジャックは悪魔に「地獄へ連れて行ってほしい」とお願いしましたが、 生前「魂を永遠に取らない」と悪魔に約束させていたため、その願いは聞き入れられませんでした。 それが死後になって裏目となり、天国にも地獄にも行けなくなったジャックの行き先は、 灯りひとつない暗闇です。 ジャックは悪魔のお情けで地獄の火を分けてもらい、 転がっていたカブをくりぬいてランタンの代わりにしました。 ジャックはこのランタンを頼りに、今もひとりで暗闇を彷徨い続けています。
民話では、道端に転がっていたカブをジャックがくり抜いて火を灯したことが始まりといわれており、ハロウィンにおいても本来はカブでランタンを作っていました。
しかし、ハロウィンがアメリカに伝わった際にカボチャの生産量が多いことで、カボチャでランタンを作るようになったといわれています。

5.日本ではいつから?
日本で最初にハロウィンを行ったのは、1970年代に原宿の「キディランド」がハロウィン商品の販売を開始するなど、商業として入ってきましたが、当時の注目度は高くありませんでした。
その後、1983年に原宿表参道でハロウィンパレードが開催されるようになり、1997年に「東京ディズニーランド」がハロウィンをテーマにした秋イベントを開催するようになってから認知度が一気に高まりました。2000年代からお菓子メーカーが参入したこともあって、今ではすっかり国民的なイベントにまで成長しています。
日本では、悪魔払いが目的という仮装とは異なり、漫画やアニメのキャラクターなどのコスプレをしたり仮装し、楽しむイベントして進化しています。
クリスマス、バレンタインデーというイベントにならぶほど、ハロウィンの市場規模が年々拡大する可能性は高く、注目度が急上昇しています。
6.まとめ
古代ケルト民族の宗教行事から始まりだったハロウィンは、今や世界中に広まり、各地の文化や特性と合わさりながら発展してきました。
アメリカでは世俗的なイベントとして親しまれていて、ハロウィンの日は家をホラー風に装飾してホームパーティーを開催したり、仮装をしたりして楽しんでいます。
近年日本で親しまれているハロウィンは、アメリカから伝わった楽しみ方です。
子どもたちにハロウィンの由来や起源、仮装する意味などを話し、外国の文化により理解を深め、いっそう秋の行事を楽しんでくれるとよいですね。
ハロウィンは大人も子供も楽しめるイベントです。
ジャック・オー・ランタンを作ったり、家族や友達と仮装してハロウィンパーティーをしたり、ハロウィンをもっと身近なイベントとして楽しんでみてください!


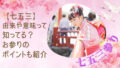
コメント